科学的視点とそうでない視点が入り混じる再エネ
第63回:価値観の棚卸しの必要性(9)

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
2024/05/15
再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。

前回は「もしトラ」の環境影響について述べたが、今回はその延長線上にある再生可能エネルギー(Renewable Energy)について述べさせていただく。
初めにお断りしておくが、この件を論じるには、本質的な環境影響への配慮、科学的環境問題への取り組みの視点とは別に、法制度上の縛り、投資家や市場からの要求という視点があることを理解しておいてほしい。

後者に関しては、時に理不尽で、科学的ではない感情論の要素が入り込みがちであり、ビジネス上の駆け引きも存在するだろう。したがって、企業の立場でこれらを無視することはできない。しかし、これだけを追い求めていては、振り回されるだけで、最悪の場合、はしごを外されてしまう危険性だってある。それは世の中の政治事情、価値観の変化で、簡単に180度変わり得る。
つまり、前者の本質論を理解したうえで、後者のルールも受け入れながら、バランスを取った経営判断をしないと、社会貢献どころか企業の存在価値すら失いかねないことを頭に置いておく必要がある。なぜなら、本質的な問題認識が優先されるべきなのはコンプライアンス的にも当たり前だからだ。
さて、前置きが長くなったが、再生可能エネルギーとは何なのかから入りたい。

再生可能エネルギーの定義は、石油や石炭、天然ガスなどの有限な資源である化石エネルギーとは違い、自然界に常に存在するエネルギーのこととされている。その特徴は「枯渇しない」「どこにでも存在する」「CO2を排出しない(増加させない)」の3点である。
法律ではどうだろう。平成21年8月施行の「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」および「同施行令」で次のように定義されている。
・非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用できると認められるもの(法第2条第3項)
・具体的な種類:(1)太陽光、(2)風力、(3)水力、(4)地熱、(5)太陽熱、(6)大気中の熱その他の自然界に存在する熱、(7)バイオマス(動植物に由来する有機物) の7種類(施行令第4条)。利用の形態は、電気、熱、燃料製品。
共通する概念として「枯渇しない」「永続的に利用できる」となっているが、果たして本当だろうか。
再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事
おすすめ記事


「災害でも医療を止めない!」令和6年能登半島地震 これまでとこれから
石川県七尾市にある恵寿総合病院の神野正博理事長に継続的な医療提供を可能にした数々の対策と被災地の置かれた現状についてお話しいただきました。2024年5月22日開催。
2024/05/28

リスク対策.com編集長が斬る!【2024年5月28日配信アーカイブ】
【5月28日配信で取り上げた話題】今週の注目ニュースざっとタイトル振り返り/特集:災害時におけるオフィスのトイレ対策
2024/05/28
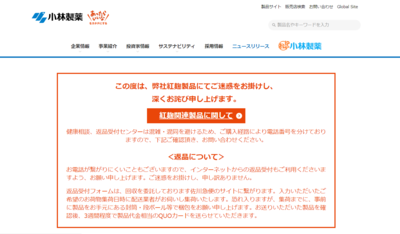




釜からこぼれた亜鉛で火災 BCPが初動の背中押す行動指針をもとに「大げさな対策」無駄に終わっても賞賛
1月1日の能登半島地震でシーケー金属の本社工場ではメッキ用の釜からこぼれた亜鉛が原因で火災が発生した。同社は消防団の協力を得て鎮火させるとすぐに、事業再開に動き出す。復旧活動にはげむ従業員の背中を力強く押したのは、東日本大震災の被災経験をもとに策定したBCPの社員行動指針だった。
2024/05/22
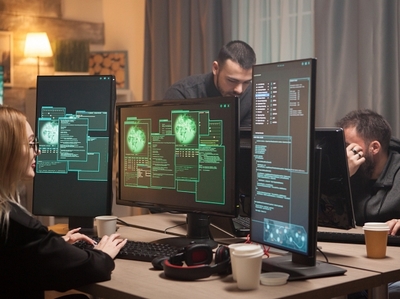
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方